
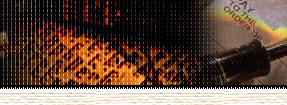
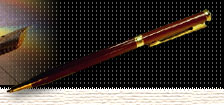
 |
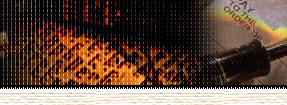 |
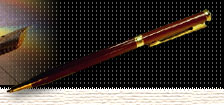 |
|
FE短編小説 -聖戦の系譜-
風の詩(フュリー) その羽は風をはらんで、高く舞い上がった。 悲しい気持ちになった時、私はいつも空を駆ける。 ペガサスにまたがって、受ける風はとても優しい。 優しい風はいつも私とともにある…緑色の柔らかい髪が、風になびいている… その色は、真夏の草原の色、綺麗で強い風の色… 頬に触れた手が暖かい。 「フュリー」 名前を呼ぶ声がとても愛しい。 愛しいあの人はいつも私の側に、そして、いつも私の手の届かないところに… どこまでも続く草原を二人の子供が駆け回っていた。 緑色の髪と緑色の瞳が印象的なその子供達は、伸びやかな肢体を惜しげもなく発揮させ、猫の兄弟のようにじゃれあっていた。 その二人を美しい緑色の髪を風にたなびかせた一人の女性が優しく見守っていた。 二人の子供、セティとフィーの母親、フュリーであった。 深い緑の瞳の奥に燐とした強さを持つ、美しい女性だった。 彼女の側には、まるで彼女を守るかのように白馬が従っていた。 白馬には美しい二対の羽があった。白馬は時たま鼻を彼女にこすりつけては満足そうに鼻を鳴らしている。 澄んだ青空の昼下がりのことだった。 「母様、見てください。空が泣いている…」 小さなセティの手が澄んだ遠い青空を指していた。 セティの指差すもの、それはグランベル帝国、バーハラ…。フュリーは唇を軽くかんだ。 「…どうして、空が泣いているってわかるの…?」 フュリーが優しく尋ねると、セティは深く澄んだ緑色の瞳を伏せてつぶやいた。 「風が、囁くんです。あの空は助けを求めてる、って」 フュリーは自分のひざで眠っているフィーの頭を軽くなでながら、言葉なく微笑んだ。 この子も、やはり風の運命を背負っているのだわ… いつか、セティも自分の側から離れていくであろう事をフュリーはその時実感した。 言葉を紡がない母にセティは不安を感じたのか、瞳を揺らせながら言った。 「父様が…僕を呼んでいるのかもしれません。」 フュリーの脳裏に4年前のバーハラの情景がよみがえった。 爆炎に全てが飲まれた悪魔のような戦い…名のある公子や王子がその戦いで大勢命を失った。 その熾烈な戦いの中、フュリーとその夫、シレジア国王レヴィンは奇跡的に生き延びた。 戦い後レヴィンは、一時シレジアに引きこもったが、大地に染みた戦いの血が乾きもせぬうちにフュリーと幼い二人の子供を残し、シレジアを去った。 フュリーはそれを恨む事はなかった。 自分の知っている「レヴィン」である彼の中に、もう一人の「レヴィン」の姿を見たからだ。 それは、言葉に表せるものではなく、感覚で感じられる存在だった。 ただ、離れる悲しみを忘れる事など到底できはしなかったけれど。 「父様がお呼びに…?…セティはどうしようと思うの…?」 フュリーはセティの体を優しく引き寄せるとやっとその一言を口にした。 セティは力強くフュリーを見つめると、口を開いた。 「本当にそれが僕を呼んでいる声ならば…それが父様であってもそうでなくても…」 しりつぼみではあったが、その言葉にはセティの決心が強く感じられた。 この幼い魂にどれだけの勇気と正義が満ちているか… 嬉しい気持ちと悲しい気持ちがフュリーの心の中で揺れた。 「私はあなたをとても誇らしく思うわ…さすが父様の子ね…愛しい私のセティ」 フュリーは強くセティを抱きしめた。 いつか離れていくだろうセティをせめてこの瞬間だけでも自分の下に繋ぎとめたかった… 二人の子供達との生活は、フュリーに生きる喜びを与えた。全てが満たされた日々だった。 それから10年の月日が経ち、フュリーは病を患った。 軽い過労と思っていた病は確実にフュリーの体を蝕む病であった。 ベットに横になる日々が続いた。二人の子供達は、かいがいしくフュリーの世話をした。 そうした日常の中、フュリーは気が付いてしまった。 セティが、まるで風に呼ばれているかのように、グランベルの方を眺めている事に… 風が運命を急速に紡いでいるのを感じた。ついに、セティが風の勇者としての運命に目覚めたのだ。 訪れるべき時が来たのかもしれない、フュリーは思い、セティを呼び出した。 「あなたに…渡したいものがあるの…」 床の上で弱弱しくつぶやくと、フュリーはセティに古い本を手渡した。 それはレヴィンがフュリーに「セティの為に」、と渡していた魔術書だった。 魔術書がセティの手元に渡ると、どこからともなく暖かく優しい風が吹いてきて、満ち足りた空気が部屋を包み込んだ。 「これは…」 セティの顔に驚愕が浮かんだ。 「それは…あなたの父上レヴィン様があなたに残した魔道書…聖なる風の魔法フォルセティです。それをあなたを、そしてあなたに助けを求めている全ての人々を救うために正しく使いなさい…」 全てはこの時の為にあったのかもしれない。フュリーはふと思った。 セティは一瞬、逡巡した後、深くフュリーに礼をした。 その夜、フォルセティを片手にセティは一人シレジアを旅立った。 「母様…お願い、お願い…嫌、嫌よっ…」 フィーの嗚咽が室内を満たしていた。 フュリーは最後の力を振り絞って、フィーの手を自らの手で優しく包んだ。 「父様も…兄様も…こんな時に…何してるのよっ…馬鹿っ…ううう」 フィーの頬をとめどなく涙が流れつづける。 「嫌よ…母様…父様も兄様もいないのに…ダメよ…一人で逝ってはダメ…」 フュリーの瞳がどんどん力を失っていくのを見てフィーは気が狂いそうな気分でつぶやいた。 「優しい子ね、フィー……あなたがいてくれて本当に良かった…ありがとう、フィー…」 精一杯の微笑をフュリーは浮かべた。 これから、フィーが強く、優しく生きていけるように。 窓から優しい風が吹いた。 フュリーは風に攫われるかのように息を弱めた。 「フュリー」 「母上…」 目の前にレヴィンとセティの姿があった。 レヴィンはフュリーの手を優しくつかむと、その体をかき抱いた。 セティが泣くフィーの頭を優しくなでた後、フュリーを見て微笑む。 「さぁ、フュリー行こう…これからはいつも一緒だ…」 レヴィンの声に導かれ、フュリーは自分の体が風になるのを感じた… ずっと愛おしく感じていた風をついに手に入れた、フュリーはそう思った。 二人の優しい子供達に感謝した。 今まで生きてこれて本当に幸せだと思った。 二人の子供達をレヴィンを愛してこれた事を本当に幸せに感じた。 「レヴィン…様…セティ…フィー……愛しているわ…」 その羽は風をはらんで、高く舞い上がった。 嬉しい気持ちを抱き、私はいつも空を駆ける。 ペガサスにまたがって、受ける風はとても優しい。 優しい風はいつも私とともにある… 緑色の柔らかい髪が、風になびいている… その色は、真夏の草原の色、綺麗で強い風の色… 頬に触れた手が暖かい。 「フュリー」 名前を呼ぶ声がとても愛しい。 愛しいあの人はいつも私の側に、そして、いつも私はあの人の側に… |
|
| 小説ページトップ ∴ みつけたきせきへもどる ∴ 小説の書き方本 ∴ 朱沙のおすすめ小説 |